鉛筆配分問題と盗人算
 「いまクラス全員に鉛筆を均等に配りたい。4本ずつ分けると7本余り、5本ずつ分けると4本足りない。さて、クラスの人数と鉛筆の本数を答えよ。」ここでは鉛筆配分問題と呼ぶことにしよう。中学校の連立方程式を習ったときに出会った難問である。もちろん、人数をx、本数をyと置いた連立方程式を解けば答えは得られるので、数学の問題としては何の問題もない。何が難しいかといえば、その問題設定である。最初に鉛筆が何本あってクラスに何人いるかを確認しないで、配ってみたら余ったとか足りないとか言っている問題設定が想像しがたい。もし現実にそういうことをしている人がいたら、おいおい大丈夫かと心配になってしまう。少々反抗期だった中学生の私は数学の先生にそう言った。先生は一言、「いいから解け」と。思い返すとその辺りから、数学とはよくわからない問題を解く役に立たない学問だという印象を持ってしまったのかもしれない。そのせいか数学はそこそこにして、大学以降は自然科学を専門とすることとなる。
「いまクラス全員に鉛筆を均等に配りたい。4本ずつ分けると7本余り、5本ずつ分けると4本足りない。さて、クラスの人数と鉛筆の本数を答えよ。」ここでは鉛筆配分問題と呼ぶことにしよう。中学校の連立方程式を習ったときに出会った難問である。もちろん、人数をx、本数をyと置いた連立方程式を解けば答えは得られるので、数学の問題としては何の問題もない。何が難しいかといえば、その問題設定である。最初に鉛筆が何本あってクラスに何人いるかを確認しないで、配ってみたら余ったとか足りないとか言っている問題設定が想像しがたい。もし現実にそういうことをしている人がいたら、おいおい大丈夫かと心配になってしまう。少々反抗期だった中学生の私は数学の先生にそう言った。先生は一言、「いいから解け」と。思い返すとその辺りから、数学とはよくわからない問題を解く役に立たない学問だという印象を持ってしまったのかもしれない。そのせいか数学はそこそこにして、大学以降は自然科学を専門とすることとなる。
それから二十年以上の歳月が経ち30も半ばになった頃、職の関係で奈良に住むことになり神社仏閣を見て回る機会が増えた。幾つかの神社には何やら幾何学の問題のように見える算額が掛けられており、和算に興味を持ち出した。ある日市立図書館で和算の解説本を借りて週末の午後に寝ながら読んでいると、江戸時代の数学書である塵劫記に書いてあるという驚くべき問題に出会った。「いま橋の上にいて、橋の下にいる盗人が盗んだ絹の取り分を相談しているのが聞こえる。4反ずつ分けると7反余り、5反ずつ分けると4反足りない、と。さて、盗人の人数と盗んだ絹の反数を答えよ。」盗人算というらしい。これは中学の時に解かされた連立方程式の問題ではないか。しかも、問題設定が素晴らしい。見つかったら困るから橋の下を見るわけにいかないので、相談している声だけを頼りに盗人が何人でどれだけ絹を盗んだかを当てよ、という設定である。どなたか偉い数学の先生が連立方程式の例題を教科書に入れる際、泥棒の話を入れるのは教育上いかがなものかという「配慮」があり、盗人算を鉛筆配分問題に書き換えたのではないかと邪推する(真相をご存知の方はお教えください)。
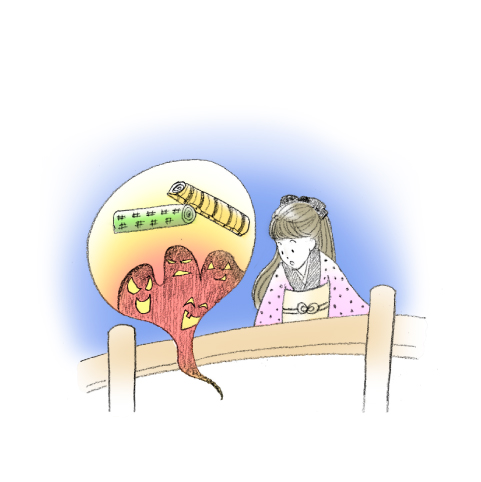 盗人算の例は、数学が見えないものを見えるようにしてくれる力を持っていることを示している。物理学の歴史を振り返ってみると、高々100年前の20世紀初頭でさえ、原子が実在のものか計算上の便宜的なものかの論争が続いていた。アインシュタインは奇跡の年と呼ばれる1905年の論文の一つで、花粉が溶液中をランダムに動き回るブラウン運動が実は見えない水分子の熱運動から生じるとし、ブラウン運動を観測することで分子を数える方法を見出した。つまり、サイズや粘性が異なる様々なブラウン運動から水分子の個数(アボガドロ数)を数えてそれが一定であれば、分子は実在するということである。その実験を細心の注意を払って行ったのはフランスのペランであり、この二人の仕事により分子の実在は疑いのないものになった。昨今、分かりやすい「見て分かる」科学分野が重宝されている風潮があるが、科学の本質は「見えないものを見えるようにすること」である。そして数学にはそれができる。もし、盗人算やブラウン運動の話を中学校で聞いていたら、数学との付き合い方が変わっていたかもしれない。いまの中学生や高校生はどのような数学の教育を受けているのだろうか?きっと「数理女子」のような場で数学の面白さを知る機会が増えていて、私のような回り道をしなくてもよい方向に進んでいるのだと期待したい。
盗人算の例は、数学が見えないものを見えるようにしてくれる力を持っていることを示している。物理学の歴史を振り返ってみると、高々100年前の20世紀初頭でさえ、原子が実在のものか計算上の便宜的なものかの論争が続いていた。アインシュタインは奇跡の年と呼ばれる1905年の論文の一つで、花粉が溶液中をランダムに動き回るブラウン運動が実は見えない水分子の熱運動から生じるとし、ブラウン運動を観測することで分子を数える方法を見出した。つまり、サイズや粘性が異なる様々なブラウン運動から水分子の個数(アボガドロ数)を数えてそれが一定であれば、分子は実在するということである。その実験を細心の注意を払って行ったのはフランスのペランであり、この二人の仕事により分子の実在は疑いのないものになった。昨今、分かりやすい「見て分かる」科学分野が重宝されている風潮があるが、科学の本質は「見えないものを見えるようにすること」である。そして数学にはそれができる。もし、盗人算やブラウン運動の話を中学校で聞いていたら、数学との付き合い方が変わっていたかもしれない。いまの中学生や高校生はどのような数学の教育を受けているのだろうか?きっと「数理女子」のような場で数学の面白さを知る機会が増えていて、私のような回り道をしなくてもよい方向に進んでいるのだと期待したい。
※2016年3月掲載。情報は記事執筆時に基づき、現在では異なる場合があります。
著者略歴

趣味:不器用な電子工作
座右の銘:「すべてのことは出来ないといった瞬間に不可能になり、できるといった瞬間に可能になる」(アントニオ猪木「闘魂記」からのうろ覚え)



